首都圏住民にとって、東南海トラフ、首都直下地震、富士山噴火が連動して起こったらどうなるかを想像して書いてみる。必要な用意が何かを真面目に考えたい。
その朝、日本は壊滅した
20XX年X月X日、午前5時。その瞬間、私は家族と東京郊外の自宅にいた。携帯の緊急地震速報が一斉に鳴り響いた。
首都圏は震度6強。経験したことのない揺れだった。縦、横、あらゆる方向からの激しい揺さぶり。家の構造体は呻きを上げ、壁や天井は激しく軋む。固定されていない家具はなぎ倒され、きちんと閉まっていなかった食器棚から食器が床に落ち砕け散乱、家の中はめちゃくちゃになった。
テレビでは東南海トラフ地震、首都直下地震、富士山噴火が連動して起きたことを報道していた。そして、千葉から東海、四国、九州まで強い津波警報。そこまで見たとき、室内は停電により闇に包まれた。テレビは消え、携帯もつながらない。
外は異様な静けさだったが、遠い西の空が黒く染まり始めた。富士山が噴火した。
首都圏は3つの致命的な災厄に同時に襲われた。
- 物理的破壊:東南海トラフ、首都直下地震による建物の倒壊、液状化、火災、津波。
- 全ライフラインの停止:電線への降灰による断裂で、全面的な電力復旧までは少なくとも数か月かかりそう。当然、通常の仕事もできないし、電話もつながらない。ネットはサーバーや通信基地局によるのか、つながるページがいくつかある。
- 降灰:風に乗って首都圏を覆い尽くす富士山噴火による「死の灰」。この降灰は、約2週間にわたって降り続く。
その日から、関東から九州までの太平洋側地域において一切の生産的な活動がストップした。
発災当日
自宅は奇跡的に倒壊を免れたが、外は瓦礫と、数センチの灰で覆われていた。携帯はつながらない。全ライフライン停止。食糧は備蓄も含めいくらかあるが調理はできない。冷たい食事を摂り、簡易トイレをはじめて使用。
ノイズだらけだがラジオは使えた。近所の避難所を訪れてみると人々は集まっていたが当然まとまった物資の配給などない。スーパーにも物がないし、入ってくる見込みもない。自販機も即売り切れ。
その日は不安のなか夜を迎えた。この状態がいつまで続くのか。
発災翌日~1週間
町内会や自治体から避難所に救援物資の提供がはじまったが、全員には行き渡らなかった。避難所への移動も考えたが、ごった返す空間は精神衛生的にも不安があり、感染症のリスクもある。自宅に留まり、なんとか過ごした。
幹線道路さえいまだに灰に覆われ車の通行はできず、物流網は完全に停止。地域の備蓄も尽き、餓死者が出始めるのも時間の問題だった。
発災から1ヶ月―「死の灰」の下で耐え忍ぶ
10万人以上の死者、数十万人の負傷者が出たとの情報。病院はパンク。瓦礫と火山灰に阻まれ、救助や支援は乏しい。
備蓄と水の命綱:ストックした食糧、水が頼りだった。食糧と水はすぐに厳格な配分を開始。水は、自宅裏の川の水をポータブル浄水器で濾過し、カセットコンロで煮沸して飲んだ。このおかげで、なんとか生きながらえた。
火山灰との闘い:家を密閉。2週間にわたる降灰は、家の周りに厚く積もり、ガラス片等を含む灰を吸い込んでしまうことは健康被害のリスクを伴った。
この間、物資輸送の生命線となる動きもあった。
大きな幹線道路だけは、灰除去の特殊車両によって整備が進められ、物資輸送の大型トラックと緊急車両だけが通行を許可されていた。一部の自治体が運営する避難所には、限定的ながら物資が届き始め、その避難所へアクセスできる人々はなんとか当面をしのぐことができた。
一方で生命の危機下では、秩序の崩壊と「人間の悪意」も表面化してしまう。
災害の規模が巨大すぎて「公助」が機能せず命の危険を感じるとき社会秩序は壊れ始める。発災から数日が経つと、絶望感と飢餓感が人々を蝕む。
店舗や避難して無人となった家屋では、略奪や盗難が横行した。自衛のための武器を手に取る者も現れ、夜になると暴行や盗難の噂が広まった。自宅の戸締まりを強化してもガラスなど簡単に破られ、民間警備会社もアテにならない。フェイクニュースもはびこり、誰もが見知らぬ人に対する猜疑心が強くなってしまった。
物理的にも精神的にも地獄であった。
餓死への危機感と脱出への決断
私たちがいた地域は、その「物資が届く避難所」へのアクセスすら困難だった。
1ヶ月も救援物資が乏しいと、人間は餓死する。特に体力のない高齢者や病人は、災害関連死も含め命を落とした。九州から首都圏までの数千万人のうち、どれだけの人がこのまま命を落とすのか。
自宅の備蓄が尽きかけ、食料と水が極度に少なくなったとき、決断を下した。
「首都圏に留まっても、通常の仕事ができる見込みもない。これ以上は飢え死にする」
幸いにして、家の車は4WD。火山灰が積もる道路走行は2WDより若干マシだろう。埼玉から北への道路はなんとか通行可能とのラジオやネットでの情報も得た。ガソリンは半分以上ある。平時であれば400kmくらい走行できるが、無給油だとして埼玉を抜けられるかどうか。
私たちは、残りの食糧と水をかき集め、北の方面への避難を開始する。目的地は、安全が確保されやすいと見込んだ東北方面。
死の灰を越えて―過酷な北上
こんなこともあろうかと念のため用意しておいた車のエアクリーナーの交換用フィルター、ダクトテープ、そしてエンジンを火山灰から守るための工夫を多少ほどこした。発災から約1ヶ月半。マスクとゴーグルを着用し、車に乗り込んだ。
渋滞とわずかな公助
なんとか国道4号に出ることに成功した。しかし、そこには既に同様の考えと思われる車で激しい渋滞が発生していた。多くの人々が、この「死都」を脱出しようとしていた。
車は時速20キロにも満たないノロノロ運転が続く。火山灰が深く積もった場所では、4WDでもタイヤが空転する。他の車がスタックして道を塞ぎ、渋滞はさらに悪化した。
幸い、埼玉に入ると、高速道路のSAなど、ところどころに避難所や物資供給のスペースが出来ていた。しかし、数時間並んで500mlの水数本とわずかな食糧をもらえる程度。このわずかな支援も、多くの人々が命を繋ぐためのギリギリのラインだった。
降灰の終わりと新しい希望
数日かけてなんとか栃木に入った。栃木までくれば、車の流れはややスムーズになり、降灰もほとんどない。首都圏の人間にとっては、まるで別世界だった。
被害が比較的少ない地域で、途中、なんとか給油にありつき、食料の配給がある避難所などに立ち寄りながら、1週間かけて福島までたどりついた。福島に入ると、さらに状況は一変していた。
過疎地が過疎でなくなる
福島は、首都圏から避難してきた人々でいっぱいだった。
過疎化が進んでいた地域も、いまや過疎地ではなくなった。幸い、空き家が多いため、時間をかければ自治体から住む場所の提供は期待できそうだったが、これだけの人々を養うほどの食料はすぐには用意できない。
人々は、さらに北へ北へと進んだ。
私たちは、宮城のとある集落で、なんとか空き家を借り受け、自力での生活再建を目指すことにした。
この大災害で、首都圏人口3000~4000万人のうち2~3割が、私たちのように北関東、東北、北陸、北海道へ散らばっていった。
電気・ガスのない、電話も繋がらない生活がさらに1カ月続いた。しかし、ここでは川の水はきれいで、飲み水の確保には困らなかった。わずかながら畑を耕すこともできる。食料はまだ乏しいが、自治体からの救援物資もあり餓死する恐怖からは解放された。
極端なインフレ→自給自足に近い生活を余儀なくされる
日本の生産活動がストップ、国債は暴落した。市場において円は無価値に等しく、輸入品は買えなくなった。元々自給率の低い日本。現金は紙切れではないものの、市場に商品が流通しないため、極端なインフレが発生した。
食糧を法外な高値で売る輩も現れる。ガソリンも闇市場で取引され、価格は青天井。ATMもほぼ使えず、貯金や投資資産は意味をなさなくなった。
「物々交換」と「自給自足に近い生活」が、生存のための手段になる。
まとめ
予測によれば30年以内に高い確率で東南海トラフ、首都直下地震に襲われるわけだ。さらに東南海トラフと富士山噴火は連動する可能性が高く、つまり首都圏は上記のような状況になる可能性が高い。そして生きていくために脱出せざるを得ないという現実が起きる。
今まじめに備蓄が出来ていないのは、正常性バイアスによる。これまで大丈夫だったのだからという無意識が危機への備えの阻害になっている。想像力も足りていないので、上記のように書いてみた。
その時に備えて少なくとも1か月分くらいの食糧、水、その他必要そうな物品を用意しておくべきである。


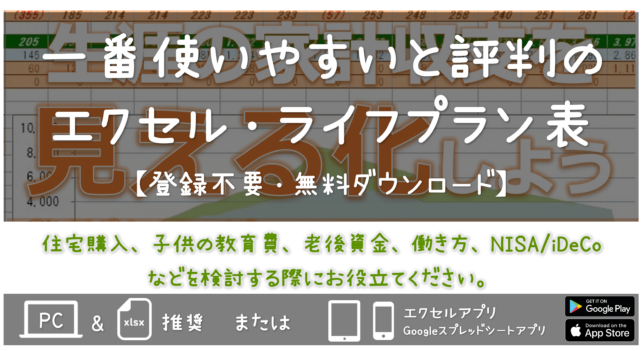
コメント